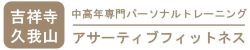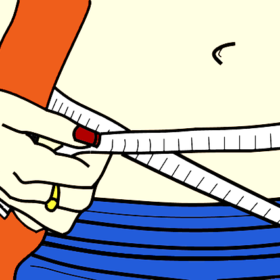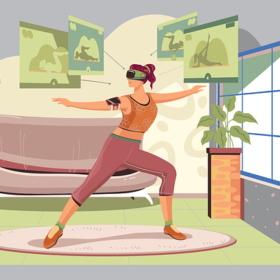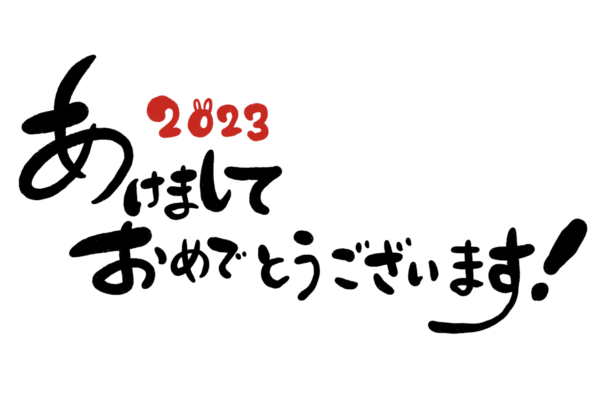
【吉祥寺・久我山】アサーティブフィットネス、パーソナルトレーナーの小森祐史です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
何度か取り上げているテーマですが、2023年の1回目は「ダイエット目標の立て方」を考えたいと思います。
「1年の計は元旦にあり」といいますが、立てた目標がなかなか実現しないのも事実。
元旦はもう過ぎてしまいましたが💦
ここから立て直してスタートダッシュを切りましょう!
目標=動因を把握する

目標が曖昧だとと何をすればいいかわからなくなります。
そこで最初は「自身の目標を把握する」作業を行います。
まずは目標を叶える意味を整理しましょう。
ここから先は目標を『動因』という言葉に置き換えます。
『動因』とは欲求や願望を意味する言葉。
一方、動因を叶える手段や方法を『誘因』と言います。
この動因と誘因が合致した時に人は行動を起こしますが、これを「モチベーションが発生する」または「モチベートされる」といいます。
具体例を出しましょう。
例えば、今のあなたは「コーラが飲みたい」という欲求(動因)を抱えているとします。
歩いているとコーラが購入できる自動販売機(誘因)を見つけました。
その時、あなたはお金を入れてコーラを購入するはずです。
「コーラが飲みたい」という動因に対し「コーラが購入できる自動販売機」という誘因が提示されたので、「お金を入れてコーラを購入する」という行動を起こした(モチベーションが発生した)のです。
このように動因と誘因が合わさったときに誰もが行動を起こします。
ですが、ダイエットは複雑かつ時間もかかる行動なので、動因が具体的でないとうまくいかないことが多いです。
例えば
「痩せたい」
「膝周りの痛みを取りたい」
「ヒップアップしたい」
では、動因が大きすぎるため「いつまでに」「どれくらい」達成したいか分かりません。
そこで次は動因を具体的な形にして位付けを行います。
動因を具体的な形にして順位付けをする
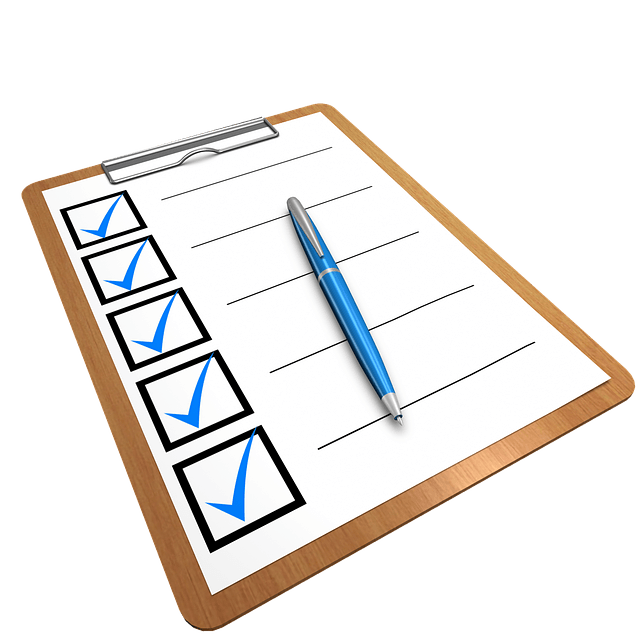
動因を把握する際は期日や具体的な目標を紙に書き出してください。
「8月までにSサイズのパンツが履けるように痩せたい」
「大好きな登山を続けられるように膝周りの痛みを取りたい」
「お尻のラインがきれいに見えるようにヒップアップしたい」
そして動因を具体的にする時は『なぜその動因なのか?』を考えましょう。
「8月までにSサイズのパンツが履けるように痩せたい」理由が「3か月後、10年ぶりに同級生に会うから」ならば、『10年前の写真をトレーナーに見せてパーソナルトレーニングで体を作り直す』という誘因が見つかります。
期日がもっと先ならば「動画や本で勉強しながら運動を始める」や「ジムに通う」も誘因になるでしょう。
このように『なぜその動因なのか?』を意識して具体的な言葉にしてください。
そうすると自分に必要な誘因がわかってきます。
動因が具体的になったところで順位づけを行います。
今あなたが紙に書いた動因を見直してください。
1つや2つではなく10、20とたくさんの動因が紙の上に並んでいると思います。
このように人の欲求や願望は計り知れないほど深いものがあります。
ですが、時間や能力の問題で全ての動因を同時に叶えることは不可能です。
なので動因には優先順位をつけていきます。
①大好きな登山を続けたいので膝周りの痛みを取りたい
②8月までにSサイズのパンツが履けるように痩せたい
③お尻のラインがきれいに見えるようにヒップアップしたい
仮に今あなたの動因がこの順番ならば「まずは病院で膝の状態を見てもらい、次に運動や食事の見直しを始める。そして有酸素運動で体脂肪を落としながら、お尻の筋トレを行う」という見通しが立ちます。
このように順番つけることで無理のない計画が立てられ、その動因が叶う確率は高まります。
定期的に動因を見直す

動因を把握し誘因と一致させること。
その際に動因を具体的にして順位付けを行うこと。
この作業ができていれば目標に向かってスムーズに行動ができるようになります。
最終段階で行う作業は「動因の見直し」です。
その時の環境や気持ちによって動因の順番や内容は変わります。
例えば、あるお客様は、「ウェストを10cm落としたい」という動因が、ある日「足腰を鍛えてマラソンに挑戦したい」に変わったことがあります。
食事をする時も
「今日はヘルシーにお蕎麦にしよう」
「脂っこいラーメンが食べたいな」
「明日は給料日だから食後にデザートも食べよう」
というようにその時の気持ちで食べたいものが違いますよね。
食べ物ほどでないにせよ、自分の動因はいつどう変わるか予想できません。
動因が変わったことに気づかないでいると、時間や労力を無駄にしてしまうことがあります。
自分はどうしたいのか?
1ヶ月に1度は動因を書いた紙を見直しましょう
ちなみに私の場合、仕事における上位3つの動因は1年に一度見直すようにしています。
叶えることができなかった動因は誘因を見直し、叶った動因はリストから外し、下位のものを繰り上げるようにしています。
もちろん今年もこの作業を行いました。
このブログでの目標は3つ
①メンタル・フィジカルの両面からダイエットの続け方を伝える
②ダイエットに限らず健康に関わる情報を発信し続ける
③一か月に1~2回のペースでブログを更新する
引き続き「運動嫌いの動因叶える」ブログ(誘因)を発信していきます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
5000人が体験した、ダイエット無料レポートをプレゼント!
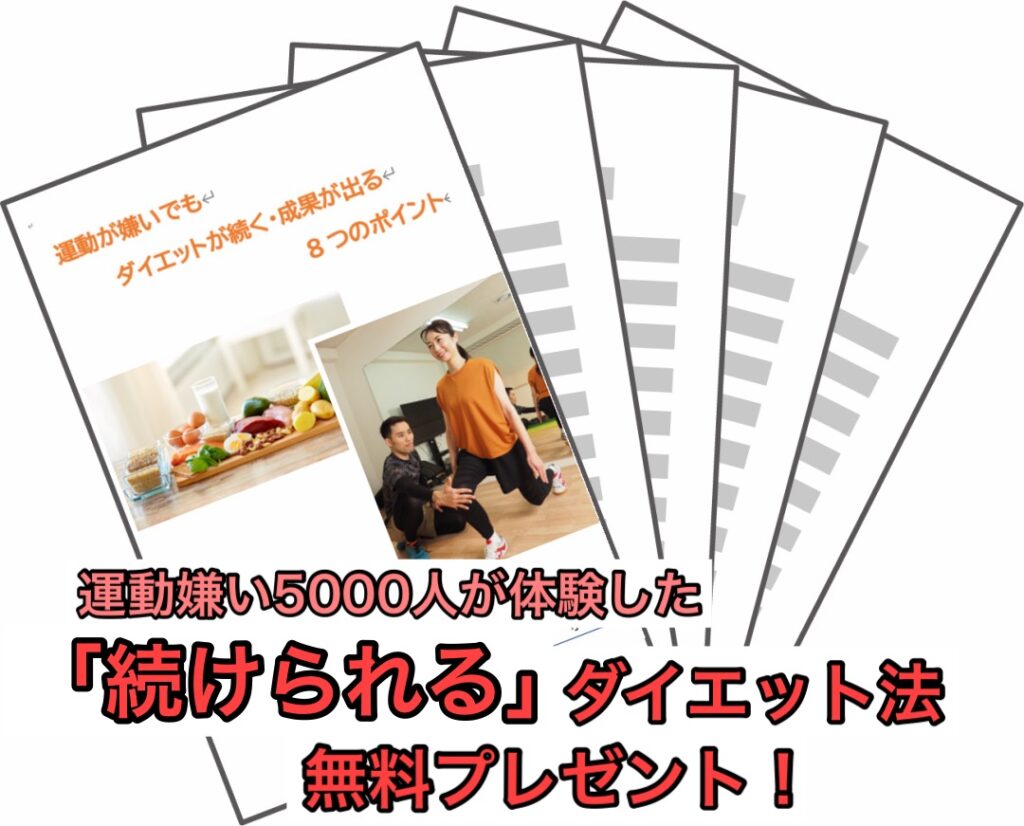
どんなに簡単な計算式も公式を知らなければ解くことはできません。
皆さんの場合、「食事」と「運動」の重要性がわかっていても「続ける方法」を知らないため、ダイエットという計算式が解けないのです。
成果が出ないのはエクササイズよりも「続かないこと」が大きな理由で、ダイエットも勉強、仕事、恋愛と同じように「モチベーション」が重要です。
そこで、このレポートでは今までの指導経験から導いた「運動が嫌いでもダイエットが続く・成果が出る8つのポイント」をみなさんにお伝えします。
あなたがもし
本気で身体を変えたい
ダイエットを続けられるようになりたい
運動習慣が身につく方法を知りたい
きついトレーニングに耐えられるメンタルを身に付けたい
とお思いでしたら、ぜひこの無料レポートを手にしてください!
関連記事