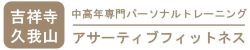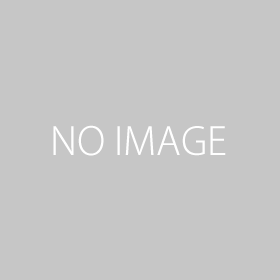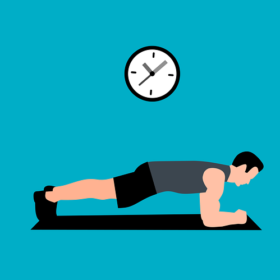【吉祥寺・久我山】アサーティブフィットネス、パーソナルトレーナーの小森祐史です。
ダイエットで成果を出すなら「食事」と「運動」どちらも大切です。
筋力トレーニングで筋肉を増やし、有酸素運動で体脂肪を燃やします。
また、筋肉量が増えるよう食事の内容を見直すことも必要です。
片方だけでは思った通りの結果は出ません。
食事を変えるだけでは筋肉が落ちてしまうこともあります。
筋肉量が減るとエネルギー消費量が低下する(詳しくは後述)ので、内臓脂肪も落ちづらくなります。
そうならないように運動は続けなければいけません。
前回までは「食事」に焦点を当てましたが、今回は「運動」に焦点を当てます。
前回の記事を読んだ後はこちらもお読みください。
下半身の運動で基礎代謝を上げる
ダイエットで筋力トレーニングを行う理由は、筋肉量を増やして『基礎代謝』を上げるためです。
『基礎代謝』とは人が生きていく上で最低限必要なエネルギーのことで、何もしていない状態でも常に心臓は動き、呼吸はしていて、エネルギーは消費されています。
一般的に1日の総エネルギー消費量の約60~70%を占めていて、筋肉量や体重によって増減します。
(50㎏の人なら1200kcal 70㎏の人なら1600kcal)
この基礎代謝の数字が高いほどエネルギー消費量は大きくなり「痩せ」体質になれますが、逆に数字が低いとエネルギー消費量が小さくなるため体重は増加しやすくなりす。
先述の通り、食事を変えるだけでは筋肉量が減るため基礎代謝は低下します。
では、効率的に筋肉量を増やすためには身体のどのパーツを鍛えればよいのでしょうか?
ずばり、私のおすすめは下半身です。
というのは、下半身の筋肉量は上半身に比べて約2倍あり、その分エネルギー消費量も多いからです。
お腹痩せには”階段のぼり”が有効です
下半身の筋肉量を増やすトレーニングには「沈み込みウォーキング」があります。
お部屋の中で身体を動かしたい方におすすめの方法です。
膝や股関節を深く曲げることで、大殿筋や大腿四頭筋などの筋肉を鍛える効果があります。
この2つは下半身の中でも特に大きい筋肉なので、その分基礎代謝が上がりやすくなります。
普段、外出することが少ない方はこのトレーニングにチャレンジしてみてください。

そして「外出はするけど運動習慣がない」という方は、移動の時に階段を使うようにしましょう。
「階段を上る」という動作も膝と股関節を深く曲げる運動で、下半身の筋肉量を増やすのに適しています。
この方法は疲労で仕事に支障を出したくないにもおすすめです。
というのは、1日の中で階段を使う時間はせいぜい5~10分程度です。
10~20回の運動を3~5セット繰り返す筋トレに比べてそこまで長い時間ではないため、疲労はほとんど残りません。
実際に私のクライアントは40~50代の方が中心ですが、「階段上り」を始めて仕事に支障が出た方はいません。
慣れないうちはハードルが高いので、「行きの通勤の時だけ」「自宅のマンションに帰る時だけ」と最初はルールを緩めましょう。
慣れてきたら「行き帰りの通勤」「会社のビルと自宅のマンションでの移動の時」と徐々にハードルを上げていきます。
ちなみに私がデスクワークの仕事をしていた時に、部署間の移動を全て階段に変えた人がいました。
自社ビル18階の全フロアを脚だけで移動していたそうですが😱、体重が9Kg減少して健康数値が改善したそうです。
そのことが社内報に掲載された後は、階段で移動する人が増えたことをよく覚えています(笑)
さすがにそこまでハードルを上げることはできませんが、階段を使うことはお腹痩せに大きな効果があります。
これからは脚を使うことを普段から意識してみてください。
もちろん「沈み込みウォーキング」と「階段上り」両方行えば、その分効果も大きくなります。
5000人が体験した、ダイエット無料レポートをプレゼント!
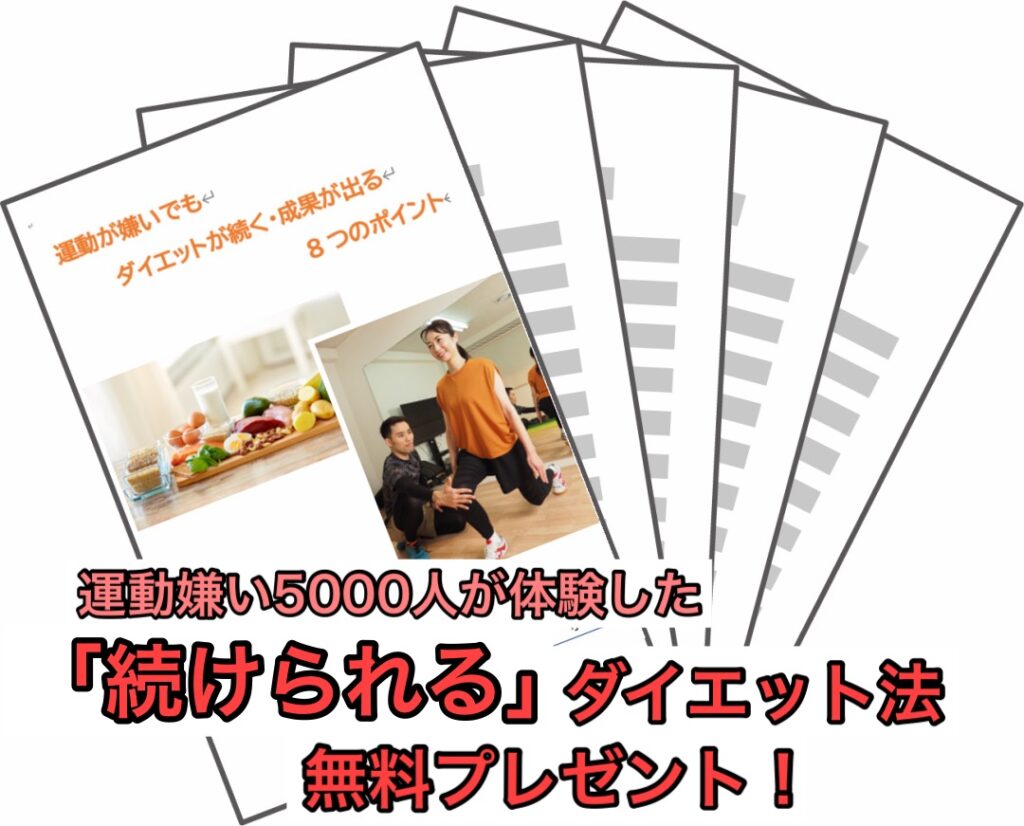
どんなに簡単な計算式も公式を知らなければ解くことはできません。
皆さんの場合、「食事」と「運動」の重要性がわかっていても「続ける方法」を知らないため、ダイエットという計算式が解けないのです。
成果が出ないのはエクササイズよりも「続かないこと」が大きな理由で、ダイエットも勉強、仕事、恋愛と同じように「モチベーション」が重要です。
そこで、このレポートでは今までの指導経験から導いた「運動が嫌いでもダイエットが続く・成果が出る8つのポイント」をみなさんにお伝えします。
あなたがもし
本気で身体を変えたい
ダイエットを続けられるようになりたい
運動習慣が身につく方法を知りたい
きついトレーニングに耐えられるメンタルを身に付けたい
とお思いでしたら、ぜひこの無料レポートを手にしてください!