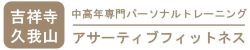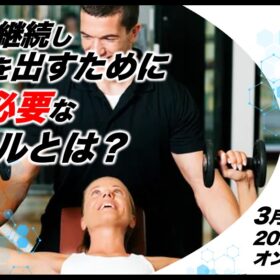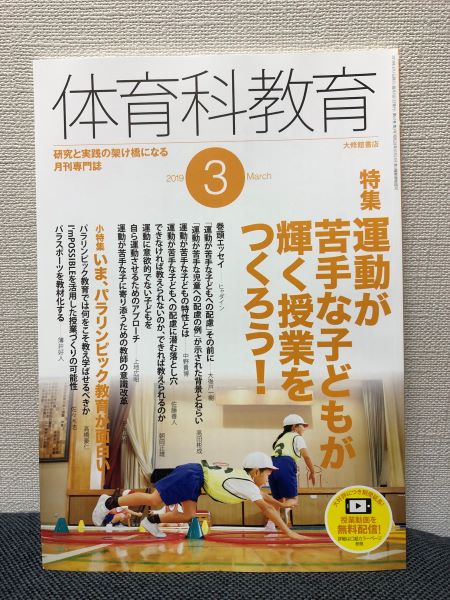
【吉祥寺・久我山】アサーティブフィットネス、パーソナルトレーナーの小森祐史です。
今回はSNS上でトレンド入りした「運動嫌い」に関する話題を取り上げます。
記事を書くきっかけになったのは『体育科教育 2019年3月号』(大修館書店)。
この号の特集は「運動が苦手な子どもが輝く授業をつくろう!」でしたが、巻頭エッセイの内容がSNS上で大きな話題となりました。
というのは、執筆者の紡ぐ言葉の一つ一つがその特集を根本から否定するものだったからです。
エッセイを担当したのは「運動嫌い」の音楽プロデューサー、ヒャダインさん。
以前から大人の運動嫌いを減らす活動を行っていた“元運動嫌い”の私にとって、ヒャダインさんが書かれた文章はとても共感できるものでした。
今回はエッセイとYoutubeの内容を引用をしつつ、パーソナルトレーナーの立場から「どうしたら大人の運動嫌いが減るのか?」を考えてみたいと思います。
体育の授業も教師も嫌いです

「僕は体育の授業が嫌いです。体育の教師も大嫌いです。」
巻頭エッセイの書き出しはこのようなものでした。
体育という授業科目だけでなく職業そのものも否定しています。
その後も体育(教師)に対する言葉は続きます。
「(うまくできないことに)体育教師がフォローに入ろうがそれはただの哀れみ」
「なぜ自分がやりたいといったわけでもない、この歪な科目に時間と体力を使わねばならないのか?」
「(運動が得意な子は輝いているという考えに対し)上から目線の差別意識丸出し」
そして最後は
「うまい人、やりたい人はやればいい」
「できない人はそっとしておいてほしい」
「どうせあなた達には我々の気持ちはわからない」
「以上です。ありがとうございました」
と半ば諦めの境地に入った言葉で締めくくられていました。
ヒャダインさんが運動している動画を観てみました
ヒャダインさんがここまで体育嫌いである理由を知りたくて、ご本人が運動している動画を観てみました。
爆笑!秋の陰キャ大運動会!ヒャダインと波乱の運動能力テスト!
【スポーツテスト】実は中川翔子とヒャダインの運動神経が…
同じく体育嫌いのタレント中川翔子さんとスポーツテストを行う企画です。
一本目の動画の冒頭から「スポーツテストって心から憎んだ」とお話をされていることからも改めて体育嫌いであることがわかります。
コメント欄でも
「体育大嫌いだった」
「他人に迷惑かけないように一生懸命やってた」
「運動神経が悪い人にとって体育はつまらない」
「運動できる人から怒られたり呆れたりされた」
など、お二人に共感している言葉が多く並んでいました。
いかに世の中に“体育嫌い”が多いかを表している動画だったと思います。
しかし、当のお二人は収録を終えてその心境に変化があったようです。
生まれて初めてスポーツで笑った
さらに動画を探したところ、スポーツテストを振り返ったお二人の対談がありました。
【中川翔子④】『体育できなくても人生楽しいんだよ』HYADA in my room #020 | Guest:Shoko Nakagawa_4
こちらの動画では、
「子供の頃にスポーツをやって楽しかった経験はない」(ヒャダインさん)
「冬のドッヂボールは地獄」(中川さん)
「運動しているところを見られたくないと思ってやっていた」(中川さん)
「磔の刑にされている気持ち」(ヒャダインさん)
「体育の授業で失笑・冷笑された」(ヒャダインさん)
「ドッヂボールで顔を狙われていた」(中川さん)
「走り高跳びで飛べなかったのが自分だけ」(ヒャダインさん)
など、節々で義務教育でのトラウマを語っていました。
これでは体育が嫌いになるのは当たり前ですね。
しかし収録は楽しかったようで「生まれて初めてスポーツで笑った」など全体的に笑顔の絶えない対談でした。
3つの動画を観て分かったことは、ヒャダインさんも中川さんも「体育の授業は嫌いだけど運動は嫌いではない」ということです。
走り出しで転んでしまっても、蹴ったボールが明後日の方向に飛んでしまっても、ボールがネットに入らなくても終始楽しそうに身体を動かしていました。
体育の授業は“運動嫌い”を増やしているかもしれない

先述のエッセイで「体育は歪な科目」と言い切っていたヒャダインさん。
同時にこんなことも書いています。
「体育とスポーツは同じものではない」
「スポーツ観戦は楽しいもの」
「しかし体育で惨めな目に合うことでスポーツまで嫌いになる」
体育の授業の問題はここにあるのかもしれません。
『人生脚本』という心理学の理論において「物事を無邪気に楽しむ子供の自我(FC)」は12歳までに確立すると考えられています。
存在を認める声掛けや接し方は自己肯定感を高め、子どもの自信を育てます。
一方、存在を否定するような言葉・態度は自己肯定感を奪い、子どもの自信を喪失させる原因です。
できない人を笑ったり、下に見るような態度は明らかに運動嫌いになるきっかけとなっています。
それこそヒャダインさんと中川さんが義務教育で体験したことのように。
対談の中で中川さんが
「運動ができなくても楽しかったらいいね」
「優しい世界でいよう」
と仰っていました。
そんな社会を目指していきたいですね😉
「運動嫌い」を減らす指導・コミュニケーションとは

もともと私が運動嫌いになったきっかけも体育でした。
集団スポーツで脚を引っ張ることが多く、自信を失ってしまったことが原因の一つです。
現在はパーソナルトレーナーという仕事をしていますので“嫌い”は克服できたと思います(“好き”というレベルではないと思いますが)。
そのきっかけは日常や仕事で少しずつ自信をつけることができたからです。
社会に出てみたらスポーツが得意ではない自分でもできることは沢山ありました。
周囲の人のサポートや温かい言葉も大きな自信になりました。
『体育科教育 2019年3月号』では「子ども達が運動の楽しさを感じる瞬間」に関する調査結果が紹介されています。
この調査は「運動が得意」と答えた児童と「運動が得意でない」と答えた児童をグループ分けし、「運動が楽しいと感じる瞬間」を質問して順位付けしたものです。
報告によると「上手に運動ができた時」が一位(不得意群)と二位(得意群)、「上手にできたことを先生や友達にほめられた時」が三位(不得意群)と四位(得意群)となっていました。
やはり「自信をつける」指導やコミュニケーションは運動嫌いを減らす一つの手段になることが分かります。
『体育科教育 2019年3月号』を読んでパーソナルトレーナーが考えたこと
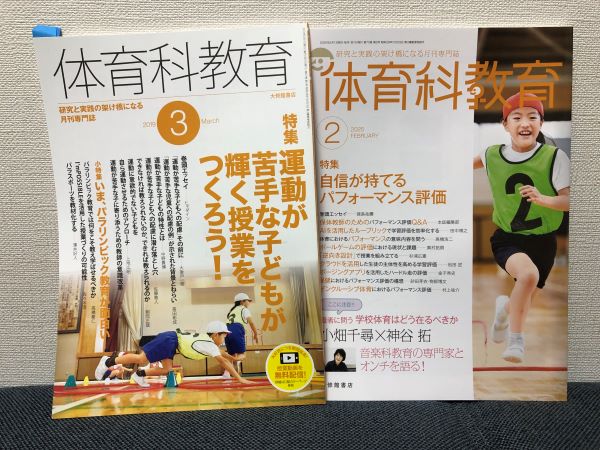
私のパーソナルトレーニングは成人した大人が対象ですので子どもとは状況が違うかもしれません。
しかしクライアントは、ヒャダインさんや中川翔子さんと同じように体育の授業がきっかけで“運動嫌い”になった方ばかりです。
最初は身体を動かすことに前向きではありませんが、うまくできた時や成果を感じるとその瞬間から運動に対して好意的になります。
そのような場面に立ち会うたびに大人も子どもと変わらないことを強く実感します。
『体育科教育 2019年3月号』の巻頭エッセイは指導の方向性を確かめるきっかけになりました。
運動が好きな方はそれほど多くはない
運動が嫌いになるきっかけの一つは体育の授業である
運動を好きになる一つの方法は「自信をつける」
ことを胸に刻んで、今後もお一人おひとりと向き合いたいと思います。
指導者の立場から見て特集記事は勉強になる内容が多かったです。
とくに体育教師やパーソナルトレーナーなど指導の現場にいる方は購入して読まれることを強くオススメします。
さらに先日発売された『体育科教育 2025年2月号』では、ヒャダインさんのエッセイに対する体育教師のコラムが掲載されていました。
こちらもオススメです!
ポッドキャストでは記事の音声版を配信しています
ポッドキャスト【現役パーソナルトレーナーが「運動嫌い」に出す処方箋】では、ブログ記事の音声版を配信しています。
ぜひ併せてお聴きください。
関連記事